無加工改造が基本のB-MAXマシンとして、おすすめなのが最新のVZシャーシ。
VZシャーシのマシンの中には、付属のパーツが優秀なマシンキットも多いです。
そんなキットを使うことで、限られた予算の中でもしっかりとしたマシン改造をすることができます。
✅この記事の内容
- 使用マシン
- 3000円分のパーツ一覧
- フロント周りのセッティング
- リヤ周りとブレーキのセッティング
- マスダンパー
この記事では、VZシャーシのB-MAXマシンについて。
パーツ予算3000円以内での改造を、パーツの取り付け方と合わせて紹介します。
無加工改造が基本となるB-MAXマシンには、付属のパーツが優れているVZシャーシを使った改造がおすすめです。
- マシン:デュアルリッジJr.
- モーター:ハイパーダッシュ3モーター
- フロントバンパー:スーパーXシャーシ・FRPリヤローラーステー
- フロントローラー:ミニ四駆ローラー用 13mmボールベアリングセット2
- フロントスタビ:ハイマウントチューブスタビセット (ブラック)
- リヤブレーキ:リヤブレーキステーセット
- サイドマスダンパー:ARシャーシ サイドマスダンパーセット
- リヤマスダンパー:ボールリンクマスダンパー (スクエア)
今回のマシンでは、ミニ四駆を始める平均的な予算の目安3000円でパーツを準備しています。
マシンキットやモーターはもちろん、各GUPをそろえることでしっかりコースを走ることも可能。
もちろん細かい部分を見ていくと、パーツが足りない部分やビスなどが不足している部分も出てきます。
しかしミニ四駆を始める最初のマシンの改造としては、かんたんで十分な改造が可能。

「マシンキット+パーツ3000円分」という組み合わせでも、コースを楽しく走らせるマシンにできます。
VZシャーシのB-MAXマシンを3000円で改造

マシンはデュアルリッジJr.

今回のマシンは、通常品番のデュアルリッジJr.を使用して改造しています。
このキットを選んだ1番の理由は、初期パーツが優れている部分です。
- 最新のVZシャーシ
- スーパーハードタイヤ
- 3.5:1のギヤ比
特に、付属のタイヤがスーパーハードタイヤという部分は大きいポイントになります。
しかしスーパーハードタイヤも硬くて跳ねづらいタイヤということで、ローフリクションタイヤと組み合わせて使われることも多いタイヤです。
さらに最新のVZシャーシや3.5:1の超速ギヤというのも、マシンを速くする上では欠かせない組み合わせ。

今回の改造の予算の中にマシン代は含めていませんが、それでも実用的で改造効率の良いマシンという理由で選んでいます。
商品リンク:タミヤ レーサーミニ四駆シリーズ デュアルリッジJr.
HD3モーターを基準にパーツを選択

今回のマシンの改造パーツは、ハイパーダッシュ3モーターを基準としてパーツを選んでいます。
- モーター:ハイパーダッシュ3モーター
- フロントバンパー:スーパーXシャーシ・FRPリヤローラーステー
- フロントローラー:ミニ四駆ローラー用 13mmボールベアリングセット2
- フロントスタビ:ハイマウントチューブスタビセット (ブラック)
- リヤブレーキ:リヤブレーキステーセット
- サイドマスダンパー:ARシャーシ サイドマスダンパーセット
- リヤマスダンパー:ボールリンクマスダンパー (スクエア)
まずこのマシンのモーターは、速さでも他のマシンに引けを取らないようにHD3モーターで固定しています。
特にノーマルモーターに比べて速度域の上がるダッシュ系モーターだからこそ、マシンの安定性を考えてパーツを選んでいます。
制振機能としての、マスダンパーはもちろん。
マシンの速度制御に欠かせない、ブレーキもパーツとして追加しています。

さらにフロントローラーを13mmボールベアリングにすることで、LCもクリアできるように改造しています。
おすすめのモーターについては、こちらの記事で紹介しています。
B-MAXマシン改造のデメリット

ミニ四駆を始めたてのB-MAXマシンの改造では、ビスやスペーサーが足りなくなるなどのデメリットも出てきます。
今回のマシンは、ミニ四駆初心者やこれから始めようとしている人にも参考にしやすい改造がコンセプト。
なので使用するビスなども、キットや購入したパーツに含まれているものだけにしています。
しかしこの場合、理想とする形に改造していくのがむずかしい場合も。
「もっと長く取り付けたい」「もう少しスペーサーで高さを出したい」などの場合も、思ったように改造できないもどかしさが。
普段からミニ四駆をやっている人からすると、何気なく使えているビスやスペーサー。

しかしゼロからマシン改造をしていくとなると、最初のうちはビスやスペーサーさえ貴重なパーツになってきます。
フロント周りの改造

19mmローラーの位置に13mmローラー

フロントバンパー周りは、あえて横幅を狭くセッティングすることでコース内に収まりやすくしています。
フロントバンパーには、スーパーX用のリヤステーを使用。
バンパー2ヶ所をトラスビスで固定し、マスダンパー取り付け用の20mmビスをシャーシの裏側から通して固定しています。
そして今回は、19mmローラー用の取り付け位置に13mmのローラーを取り付け。
しかしマシンの横幅が狭い分、ジャンプ後の着地でコースに収まる確率も高くなります。
ミニ四駆がコースアウトしないためには、ジャンプ後の着地などでしっかりコース内に収まることも重要。

少しでも安定した走行を目指すために、あえてマシンの横幅を狭めるセッティングにしています。
13mmベアリングローラー+スタビ

マシンのフロントローラーには、コースへの食いつきが良い13mmボールベアリングローラーとハイマウントチューブスタビを組み合わせて取り付けています。
今回フロントローラーには、13mmのボールベアリングローラーを使用。
しかし予算3000円という制限の中で2段アルミローラーはむずかしかったので、同じようにコースへの食いつきが良い13mmボールベアリングローラーを使用しています。
さらにフロントローラーは、15mmのビスにハイマウントチューブスタビと1.5mmのスペーサーを2個挟んでシャーシの上から固定。
フロントスタビとしての高さとしては足りませんが、手持ちのビスの中で取り付ける最善の形になっています。
13mmベアリングローラーでもプラローラーよりはコースへの食いつきは良いので、LCなどもそれなりに攻略可能。

もしむずかしい場合はフロントバンパーにワッシャーを足すなどして、スラストを確保すれば安定させることができます。
ミニ四駆のLCについては、こちらの記事で紹介しています。
リヤ周りの改造

キット付属のプラローラー+スペーサー

リヤのローラーについては、キット付属のプラローラーをスペーサーで広げることで安定性を出しています。
こうすることで、素組みの状態よりも少し上下のローラー間隔を広げての取り付けができます。
ローラーの取り付けには、ハイマウントチューブスタビとスーパーX用のリヤステーに付属のつば付き真鍮を使用。
つば付きの真鍮と大ワッシャーでローラーを挟み込み、グリスをしっかり塗ることで最低限のローラーとしての機能は果たしてくれています。
そしてローラー上部を2mmナットとスプリングワッシャーをいっしょに挟むことで、ビスの固定も安定させています。
ローラーセッティングについては、こちらの記事で紹介しています。
HD3モーターに欠かせないリヤブレーキステー

ダッシュ系モーターを使う上で欠かせないブレーキについては、リヤバンパーにリヤブレーキステーを取り付けています。
リヤバンパーには、キット付属のリヤバンパーをそのまま使用。
強度面での不安はありますが、現状のパーツではこれが限界なので走らせながらパーツを買い足していく形になります。
そしてハイパーダッシュ3モーターでの速さを制御するため、リヤブレーキとしてFRPリヤブレーキステーを取り付け。
リヤブレーキステー付属の2mmブレーキを貼るだけでも、ブレーキセッティングとしてはしっかりできています。

このセッティングでも、スロープではしっかりブレーキが当たりバンクスルーもできているのでブレーキとしての役は果たしてくれます。
バンクスルーについては、こちらの記事で紹介しています。
マスダンパー

AR用マスダンパーをフロントとサイドに

今回のマシンでは、全体的にマスダンパーを取り付けています。
マスダンパーの取り付け位置としては、フロントとサイド、そしてリヤにそれぞれ。
全体的にマスダンパーを取り付けているのも、少しでもマシンの安定性を出すためになっています。
サイドマスダンパーには、ARシャーシ用のマスダンパーセットを使用。
さらに、ボウル形のマスダンパーはフロント側の制振機能としてフロントバンパーに取り付けています。
フロントのマスダンパーの取り付けには、バンパーの固定用にシャーシ裏から通した20mmのビスを使用。

ARシャーシ用マスダンパーに付属のボールスタビキャップを使用して、マスダンパーを固定しています。
マスダンパーの種類については、こちらの記事で紹介しています。
リヤは制振効果の高いボールリンクマスダンパー

リヤのマスダンパーには、ボールリンクマスダンパーを使用しています。
ボールリンクマスダンパーの特徴は、他のマスダンパーと違ったスイング式な部分。
振り子のように動くことで、他の置きマスダンパーなどとはマスダンパーの動きとしても変わってきます。
ただしボールリンクマスダンパーの場合、付属のパーツそのままの使用ではリヤバンパーと当たってしまいます。
3mmのスペーサー3個と1.5mmのスペーサー1個で、マスダンパー可動部の長さを確保するように取り付けています。
ボールリンクマスダンパーは、固定の仕方や大きさから横ブレに弱いというデメリットもあります。

しかしボールリンクマスダンパーの制振性は高いので、最初の改造としてはモーターがあるリヤ側の制振性としても安定してきます。
VZシャーシのB-MAXマシン改造 まとめ

今回B-MAXマシンの最初の改造として使用した、3000円以内のパーツがこちら。
- マシン:デュアルリッジJr.
- モーター:ハイパーダッシュ3モーター
- フロントバンパー:スーパーXシャーシ・FRPリヤローラーステー
- フロントローラー:ミニ四駆ローラー用 13mmボールベアリングセット2
- フロントスタビ:ハイマウントチューブスタビセット (ブラック)
- リヤブレーキ:リヤブレーキステーセット
- サイドマスダンパー:ARシャーシ サイドマスダンパーセット
- リヤマスダンパー:ボールリンクマスダンパー (スクエア)
無加工改造が基本となるB-MAXマシンには、付属のパーツが優れているVZシャーシを使った改造がおすすめです。
マシンキットやモーターはもちろん、各GUPをそろえることでしっかりコースを走ることもできます。
もちろん細かい部分を見ていくと、パーツが足りない部分やビスなどが不足している部分も。

それでも「マシンキット+パーツ3000円分」という組み合わせで、コースを楽しく走らせるマシンにできます。

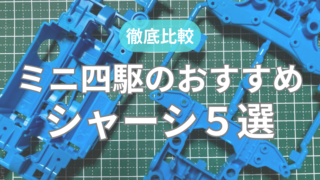
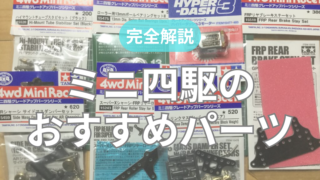
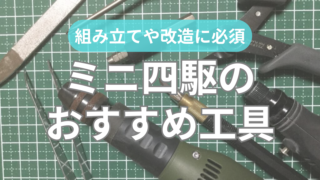
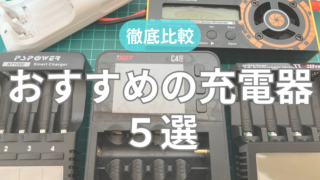

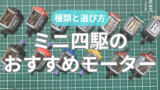
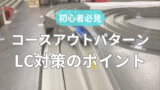
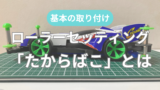
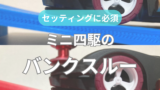



コメント